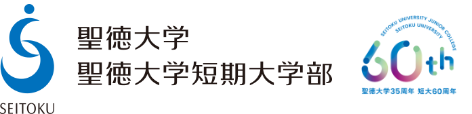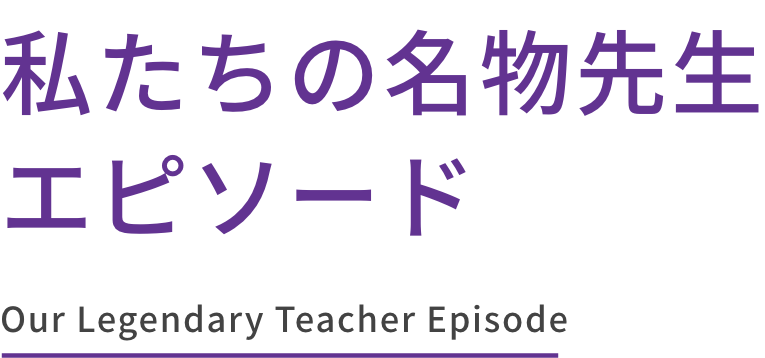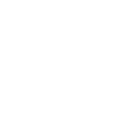川並 孝子 先生
- Episode
“学ぶ”孝子先生
「私は、昭和26年に洋裁部の本科生として入学したのですが、教室では孝子先生と同級で、一年間、机を同じくさせていただきました。それが保育部に再入学して三田幼稚園の先生になり、十年余りのご縁が結ばれたきっかけとなりました。
孝子先生はお忙しい中を授業を受けられ、黒板の小さな字が見えないと、よくおたずねになりました。『襟ぐり何センチと書いてあるの」と。それは熱心でおられました」豊田喜美子(旧姓 石坂)が語るように、このとき四十代半ばを過ぎていた孝子は、自分の半分の年齢にもみたない生徒たちと机を並べ、基礎から洋裁を学びました。和裁に関しては自ら生徒に教え、洋服も家庭で着るあっぱっぱ程度は縫っていた孝子でしたが、洋裁部の重要性が増すにつれて、経営・教職にたずさわるものとして、洋裁の理論と実際をマスターしておこうと思ったのでした。孝子は、苦労をいとわず何にでもチャレンジすることをモットーとする人であり、初歩から学ぶことに「いまさら」というためらいはありませんでした。その後、利根山弥恵子にピアノを習ったときも、教則本の『バイエル』を片手から始めました。早朝の三田校舎に、孝子の弾くピアノの音が流れました。こればかりは「生徒たちに聴かれると恥ずかしい」と、登校前と下校後の時間を選んで欠かさず練習し、それは、何年も続きました。
夏の朝、香順はその音を寝間着姿のまま、大輪の花が咲く朝顔の手入れをしながら聴きました。その頃、朝顔を交配させてさまざまな変種や大輪の花をつくり出すのは、香順の尽きない趣味でした。
いっとき集中した練習の後、孝子は校庭を丹念に掃き、校門を開け、玄関を掃除しました。前夜、教職員が掃除して帰ってからついた小さな汚れや乱れも見逃さず、すみずみまできちんと整った朝の空気の中に生徒や園児を迎えるのが、香順と孝子の信条でした。
気取らないその姿は学園経営者夫妻には見えず、時折、願書を取りに来た応募者から「おばさん」と呼ばれ、「小使さん」と思われることもありましたが、まったく意に介さない二人でした。
(出典:生誕百年記念 川並香順 総合資料集 P129 コラムより)